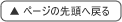島田・丸髷
女性の髪形は、時代によって違い、また身分や年齢、未婚や既婚の別によっても違った。江戸時代以前、女性の髪型は、おすべらかしと言って下に垂れ下げる垂髪であったが、江戸時代からは上へ結い上げるようになった。しかし、江戸初期には髪型も素朴であった。唐輪髷(からわまげ)は立髷の一種で、髪を頭上に集めて結んで二つ折りにし、余った髪は根本に挟むようにしたものである。
代表的な髪形は島田髷で、元は東海道・島田宿の遊女が発祥だといわれる。これが大流行し、若い女性の髪形として定着した。島田の根を高く上げて結うスタイルを高島田といい、御殿女中などに広まり、明治以後は若い女性の正装となった。現在でも結婚式などで結われる文金高島田(ふんきんたかしまだ)は、根を最も高く上げた髪形である。
一方、結婚している女性の一般的な結い方は丸髷で、いただきに楕円形でやや丸い髷を付けたもの。ちなみに日本髪の髪形は髷に代表されるが、そのほかに前髪、鬢(びん)(顔の両側にある耳の前の毛)、髱(たぼ)(「つと」ともいう。後頭部の髪を後方に膨らませた部分の回りの部位かあり、それぞれが特徴を持った。燈籠鬢、かもめ髱、鶺鴒髱などがそれで、鬢張りや髱差しなどの小道具を使って結い上げた。
男性の髪型
中世の大合戦である応仁・文明の乱(1467~77)以後、月代(さかやき)が剃られるようになり、結髪されはじめたと言われる。それまでの帽子類が取り払われ、露頂の風俗となった。髷が後頭部に結われ、元結で結った形が茶筅(ちゃせん)に似ていたので茶筅者と呼ばれた。やがて、月代を大きく剃り、髷を上にした銀杏髷が現れた。元禄(一六八八~一七〇四)頃にはさらに月代を大きくし、奴風(やっこう)な鬢をした糸鬢や、宝永(一七〇四~一一)頃の撥鬢(ばちびん)など、髪の形に工夫をこらすようになった。大きな月代で、大額などと称して意気がった。享保(一七一六~三六)頃になると、歌舞伎人気にちなんで、辰松風と言う髷の根を高くして、そり返った形も現れた。その後は、そりがゆるやかな文金風となった。
明和・安永(一七六四~八一)の頃からは、本多髷が人気を博した。この本多髷にはさまざまな形があり、男たちの通としなやかな気分を表した。一例をあげると、安永二年(一七七三)刊『当世風俗通』には八種類の本多髷が記載される。それらは「古来の本多、黒紋付」「円髷、小紋羽折」「兄様、羽祈」「疫病、黒紋付」「五分下、島衣服」「浪速、黒羽祈」「金魚、舟底とも云ふ」「団七本多、伝九郎髷とも云ふ」などとある。金魚本多は上息子風で、団七本多は侠客風と言う。疫病とはまさに腺病質風で、優男が行き過ぎると病的になるのであろうか。遊びの精神もあり、挿絵入りの面白い解説書となっている。後期に及んで、月代を大きくすることは控えるようになり、再び銀杏髷に戻った。相撲力士には、大銀杏の相撲髷などが生まれた。
櫛・笄・簪(くし・こうがい・かんざし)
それぞれ、結い上げた女性の髪を飾る小道具。木製の櫛では黄楊(つげ)がよく用いられ、漆塗りで草花や物語の絵など、さまざまな文様か描かれた。また、金箔や螺鈿(らでん)なども用いられた。鼈甲(べっこう)の櫛は高価で、江戸時代初期には大名の奥方などが使用しただけだったが、元禄(一六八八~一七〇四)のころには遊女も用いるようになった。鼈甲櫛は斑(ふ)のない飴色のものが高価だったが、斑入りのものが流行した時期もある。象牙や鼈甲に似せた馬や牛の蹄で作ったものもある。
簪はセットになる装飾品として笄がある。笄は、髪の根元から髪を巻いて髷を作る小道具だが、外に出る両端が装飾として発展した。
簪は、珊瑚玉が付いた玉簪、鼈甲製の簪、金属製で先に珊瑚や鈴などが付いて歩くたびに揺れるびらびら簪などがあった。びらびら簪は、富裕な商人の娘や武家の娘が使用したものと思われる。高級遊女が描かれた絵を見ると、高価な鼈甲製の簪を何本も差している。これは、その遊女の権勢を象徴的に示したものである。
小袖

小袖とは袖口が小さく、広袖・大袖などに対して用いられたものである。江戸時代以前、室町時代(一三三六~一五七三)から、主に上流層が表着の下に着ていた下着であった。それが次第に表着として用いられるようになったものである。江戸時代では、庶民層は最初から小袖を表着として着用した。したがって、小袖は男女を問わない一般的な日常着を指し、現在の着物の古称と言っても
江戸時代初期には、大柄で派手な文様が好まれたが、元禄期(一六八八~一七〇四)に「友禅染」(ゆうぜんぞめ)の染色技法が発案され、繊細で、かつ絵画的表現へと傾斜していく。このころには、有名な画家に小袖の絵を描かせることが、裕福な町人や遊女に流行した。一方、武家では友禅染はあまり用いられず、伝統を墨守する傾向が強かった。
小袖とともに帯が発達していくにつれ、豪華な帯に分断された小袖の文様は脇役となる。小袖の模様は裾の方に後退していき、表は無地や縞柄とし、裏だけに文様を施すものも登場した。明和・安永(一七六四~八一)のころ、女性の小袖の裏模様が流行したが、見えない場所の装飾に凝る趣向は、「粋」の美意識の表れでもあった。
羽織
羽織は、本来は防寒用の上着で、男性用として次第に装飾用としても用いられるようになった。表が黒で地味に仕立て、裏地を派手にするものもあった。将軍は、外出のとき、黒羽織を用いるので、将軍を護衛する御徒は将軍の身代わりとなれるよう黒羽織が支給された。このことを巧みに使ってオチを付けた小説に、浅田次郎の『憑神』がある。元文(一七三六~四一)のころ、女性が羽織を着るようになり、深川の芸者が羽織を着て座敷に上がるようになった。これを羽織芸者といい、江戸の「粋」を示すファッションとして人気を呼んだが、風俗を乱すことを案じた政府が、延享五年(一七四八)、女羽織の禁令を出した。このため、女羽織は途絶えるが、幕末には再び復活して、女性が羽織を着るようになる。
帯
帯は、小袖のような前合わせの衣服をまとめるために不可欠な衣料であり、江戸時代初期には「実用的なもの」だった。その帯の幅が広くなり、帯地が豪華になっていき、女性のファッションの中心となった。帯の結び位置も、「前」「後ろ」「脇」などがあったが、「後ろ」に定着した。帯地は綸子、紗綾、繻子、緞子、錦、金襴、ビロードなどが賛沢に用いられ、花鳥や物語絵などの文様が織られた。
帯幅は、はじめは二寸から二寸五分くらいであったが、寛文(一六六一~七三)頃は三寸になり、元禄(一六八八~一七〇四)頃は五寸から六寸へ、そして後期に至ると一尺以上のものも現れた。
結ぶ位置は、初期はどちらかと言うと前後脇など自由であったが、遊女は前結び、未婚者は後結び、既婚者は前結びなどの傾向性はあった。それらが次第に後ろ結びへと移行し、前結びは老年者などに限られるようになった。長さも、初期は約六尺(約一・八メートル)ほどだったものがであったのが、中・後期には一丈三尺(約三・九メートル)にもなった。結び方も色々あり、立結、島原結、一つ結、だらり紙など、さまざまな結び方が工夫された。