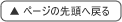江戸の食
寿司・鮨・鮓
握り鮨のことを「江戸前鮨」という。酢を混ぜた御飯に生の魚肉をのせたもので、江戸の発明である。江戸前とは江戸の前面に広がる海をいい、江戸湾でとれる新鮮な魚を使ったことから江戸前鮨の名前ができた。鮨種に使われるのは、刺身のほか、白魚、玉子、アナゴ、コハダなどで、それらの種と御飯の間にわさびを入れるなど、その様式は現在とあまり変わらない。
酢は、そもそも米に魚を漬けておくことによって発酵させ、それにともなう乳酸によって魚を保存したものである。したがって、初期の鮓は魚介を米飯の中に入れ、数日間重石を置いて漬け込んだものであった。これを馴酢(なれずし)と言う。また、食ずしと言って、米飯に酢を混ぜ、上に魚置いて上から重石で半日程度押したものが、元禄(一六八八~一七〇四)直前に現れた。そして、魚だけでなく、米飯も一緒にたべる半馴解がもたらされた。
本格的な鮓人気の始まりは、宝暦年間(一七五一~六四)に飯に酢を加えてつくる「早鮨」。しかし、このころの鮨は、箱に酢を混ぜた御飯を入れ、上に魚肉を置いて押して作る押鮨であった。振り鮨は文政年間(一八一八~三〇)のころに始まり、考案したのは両国の草屋与兵衛という者だったとされる。海苔で巻く巻き鮨ができたのも、江戸時代後期のことである。
そのころの握り鮨は、屋台で売られるファストフードで、値段も安価だった。鮨一個の値段は四文から八文、玉子は高価で一六文であった。しかし、次第に接待用の高価な鮨を出す者も出現し、中には一個三匁(銭にして二四〇文ほど)~5匁もする鮨もあったという。
初鰹
江戸前期から中期の俳人・山口素堂の「目には青葉 山ほととぎす 初鰹(鰹は「松魚」と表記)」という俳句で有名な初鰹は、春に初めて水揚げされる時期には、特に江戸の庶民の人気を集めた。女房や娘を質に置いても初鰹を買い求める風潮があったという。
安永・天明(一七七二~八九)のころは、魚屋が持って来るのを待つと味が落ちるとして、品川沖に舟を出し、鰹を積んだ舟に近寄って、金一両を投げこんで鰹一本を求め、それを食べるのが通だったという。昨今の成田空港でのポジョレー・ヌーボー騒ぎのようなものである。そのころは一両ほどだったが、文化年間(一八〇四~一八)には二~三両ほどもしたらしい。
鰹は「勝負に勝つ」という語呂から武士にも人気で、将軍家へも献上された。しかし、嘉永期(一八四八~五四)以降は次第に熱狂が醒め、安い年は金二分、それ以降は金一分ほどに下がった。
料亭
江戸で料理屋が営業を開始したのは、明暦三年(一六五七)のことだった。この年は、明暦の大火(振袖火事。一月一八日=太陽暦三月二日」があり、市街地の復興のために各地から多くの大工や左官が集まった。そこで、彼らに対して食事を提供する場が必要だったために生まれたものだと考えられる。
このころの料理屋は、奈良茶飯の店で、煎り大豆とともにお茶で炊いた御飯にお茶をかけて食べる奈良茶飯に、煮染め、煮豆、豆腐汁などを添えて出したものである。元禄(一六八八~一七〇四)のころになると、こうした料理屋が江戸に数カ所できた。これは、諸藩の留守居役の寄合などに使われたらしい。ただし、一般の庶民が使うような店ではなく、享保(一七一六~三六)の中ごろまでは、外出の途中で金を出して食事をする場所はなかったといわれている。本格的な料理屋ができるのは宝暦(一七五一~六四)のころで、『中洲雀』という酒落本には、座敷や庭の造作に凝った料理茶屋・四季庵という店が紹介されている。これなどは、料亭の走りであろう。
文化・文政(一八〇四~三〇)のころになると料亭全盛時代となり、八百善や平清などの高級料亭も出現した。このときも留守居役は主要な客だった。料亭だけでなく、庶民も楽しめる料理屋や酒場もでき、江戸の近郊では簡単な食事を出していた茶屋が料理屋に発展している。八百善が出版した料理書によると、献立は、江戸前の刺身、鮎の塩焼き、鴨肉などをメインに煮物や汁が付く現代の日本料理の原形となるものだった
蕎麦屋

蕎麦は日本産ではなく、中国から朝鮮半島を渡ってきたもので、日本では5世紀には栽培されていた。しかし、現在の線状のそば切りになったのは、江戸時代初期頃と考えられる。それまでは、粒食か餅状にした食品であった。蕎麦は、甲州から江戸に入ってきたもので、古くからあった。蕎麦屋は、元禄(一六八八~一七〇四)より前は江戸にほとんどなく、浅草にだけあった。そのころの蕎麦の値段は、七文だった。
多賀神社の僧侶慈性著『慈性日記』(じしょうにっき)には、慶長一九年(一六一四)、江戸の常明寺で「そば切り」の馳走にあった記録があり、慶長年間(一五九六~一六一五)には江戸にも広まっていたものという説もある。
享保(一七一六~三六)の中ごろから、次第に蕎麦を売る店が増えたが、そのころはまだ饂飩(うどん)(「うんどん」ともいった)屋が売っていた。専門の蕎麦屋ができるのは、宝暦(一七五一~六四)あたりからである。蕎麦を蒸籠(せいろう)へ入れて出すのは、蕎麦を蒸して出したころの名残で、丁寧なのは皿盛りにすることだった。かけ蕎麦の語源は汁をかける「ぶっかけ」から来ており、明和(一七六四~七二)のころから使われている。
江戸の蕎麦の本来の食べ方は、もり蕎麦で、塩辛い汁に先を少しだけつけて蕎麦の風味を味わって食べる。二八蕎麦が「蕎麦粉八割に、つなぎの小麦粉二割を混ぜるもの」という説があるが、実は蕎麦の値段が二×八=一六文だったからというのが本当らしい。その証拠に二七とか二五という言い方もあった。また、小麦粉を混ぜない蕎麦は正直蕎麦といい、のちにこれを生蕎麦というようになった。
一方、屋台見世の「夜鷹蕎麦」や「風鈴蕎麦」も宝暦(一七五一~六四)以後には登場した。そば湯を飲む習慣が信濃から江戸に広まったのも、寛延(一七四八~五一)以後とされる。その後、蕎麦商品も工夫が重ねられ、「三色そば」「五色そば」をはじめ、天魅羅蕎麦や鴨南ばん蕎麦などが考案されて、豊かな江戸の蕎麦食文化が育っていった。
天婦羅
てんぷらの語源は種々あると言われる。『嬉遊笑覧』(きゆうしょうらん)の南蛮菓子の項には、「何にても沙糖のすり蜜を衣にかくるをてんぷらといふ。蛮語なるべし。この故に小麦の粉を煉て魚物に付て油あげにするをもしかいふは、其形似たれば也。テンプラはもと宝石の名にもあり」として、宝石の用語例には『五雑組』(ごぎっそ)と言う中国の文献まで挙げている。また、豊臣秀吉の頃の文献にある「テンポウラ」ではないかとも言われる。これは、ポルトガル語に由来し、カトリックで肉食を禁じた日のことで、この日は魚の油料理を食べた。いずれにせよ、外来語が起源であったと思われる。
徳川家康の死因は、鯛の天象羅の食べ過ぎとされる。これは鯛を胡麻油で揚げたもので、当時京都ではやっていたらしい。その後、天魅羅は、あまり食べられなくなったようで、将軍家はもちろん、大名も食べない。
天魅羅は、屋台見世によって江戸の市民たちに楽しまれた。屋台見世が登場するのは安永(一七七二~八一)の初期ごろと推定されている。一個四文から六文であった。この屋台見世は幕末まで人形町や日本橋界隈に存在し、人形町の広野屋や日本橋の吉兵衛天魅羅が有名であった。
天明(一七八一~八九)のころには、江戸にさまざまな屋台の店ができ、江戸前でとれるアナゴ、芝海老、貝柱、はぜ、イカなどの魚介類に、小麦粉を水でといた衣を付け、胡麻油か菜種油で揚げたものである。値段は、一個四文ほどで、串にさして食べさせた。屋台だったのは、火事が恐かったからだろう。客は、江戸の庶民が中心で、安くて早く、さらにカロリーが高く腹持ちがいい天魅羅は、江戸っ子には最適のファストフードであった。高級魚を使い、店をかまえた天象羅屋が出現するのは、江戸時代も末期のことである。
上方のてんぷらは名前は同じであるが、魚をすり身状にして半円形とし(半平とも言う)、ごま油などで揚げたもので、今で言うサツマ揚げである。江戸は穴子‥えび・こはだ・貝柱などの魚介類に、うどん粉や小麦粉を溶いた衣をつけ、油で揚げたものを指す。蔬菜類(そさいるい)を揚げたものは「あげもの」と言ったので、あくまでも魚介類が中心であった。
土用の丑の日

土用は五行説から生まれた暦注(暦による日時や方位に基づく吉凶)で、二十四節気の小寒(一月五~六日ごろ)、清明(四月五~六日ごろ)、小暑(七月七日ごろ)、寒露(一〇月八~九日ごろ)の日から数えて二二日目から立春(二月四日ごろ)、立夏(五月六日ごろ)、立秋(八月八日ごろ)、立冬(二月七日ごろ)の前日までをいう。現在では太陽の位置で日が決められているが、夏の土用以外はほとんど話題にならない。夏の土用は、太陽の黄経が一一七度になる日から立秋の前の日までで、特に暦の上で十二支の「丑」にあたる日に鰻を食べる習慣がある。これは、エレキテルなどを考案した江戸時代の科学者・平賀源内が考えた他屋の広告から広まったものである。鰻はビタミンEが豊富で、食欲が失せがちな暑い時期に食べるのはそれなりの効用かある。なお、鰻の蒲焼きは上方で始まり、一八世紀初頭に江戸に入ってきた。江戸に鰻屋ができるのは天明(一七八一~八九)のころで、深川の鰻が名産だった。
水茶屋
もともと水茶屋は、京都宇治の宇治橋のたもとにあった通円茶屋が起源と言われる。名所図会にも掲載される当店は、現在、モダンな喫茶店となっているが、場所はそのままであり、往時がしのばれる。江戸吉原では、茶屋が客を揚屋(あげや)や遊女屋に案内する施設だったのに対し、寺社の門前や道筋にあって、湯茶を飲み、一休みできる店を水茶屋と呼んだ。ただお茶を飲ませるだけの店もあったが、看板娘を置いて、評判となる店もあった。江戸の町に水茶屋が増えたのは宝暦(一七五一~六四)以降のことで、ずいぶんと繁盛し、文化・文政期(一八〇四~三〇)には一町に五軒も六軒もできるようになった。
宝暦のころ、浅草寺境内の「ごくふ茶屋」という水茶屋に湊屋おろくという女がいて評判になり、江戸中の水茶屋の女がおろくの結び髪をまねするようになった。明和期(一七六四~七二)には、谷中の水茶屋「鍵屋」の笠森のおせんという百姓の娘が評判になり、浮世絵に措かれ、芝居にもなった。その他、浅草二十軒茶屋の蔦屋およし、堺屋おそで、両国広小路の高島おひさなどで、錦絵のモデルとなり、水茶屋の女の中には、実際には私娼的な存在もあったが、二股には素人の娘であることが評判を呼んだ理由である。いわば、ある種のアイドル的存在であった。当初はこのような盛り場、あるいは寺社の門前地などでは、茶屋自体は簡素な建物であり、葦簀張(よしずばり)の掛茶屋であった。また、茶汲女も法令上は木綿の着物しか許されなかったが、女色を競う職業柄、華美な模様と生地は止めようがなかった。
水茶屋の代金は、元は一服人文から一六文程度のものだったが、浅草や両国など盛り場の水茶屋では五〇文から一〇〇文ものお金がかかるようになり、有名な店では一朱(二五〇文ほど)も二朱もかかるようになった。そういう店は、入ると茶汲女が出てきて酒の相手をした。
しかし、この全盛を誇った水茶屋も、後の政治改革にともない、衰退を余儀なくされた。