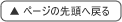江戸の行事
節句

季節ごとに定められた祝い日。人日(正月七日)、上巳(三月三日)、端午(五月五日)、七夕(「たなばた」ともいう。七月七日)、重陽(九月九日)を特に五節句という。上巳は女子の祝い日としてひな祭りが行われ、端午は男子の祝い日として鯉のぼりが掲げられる。人日には七種粥で無病息災を祈り、七夕では和歌や願い事を書いた短冊を笹竹に付けて掲げた。重陽は菊の節句ともいわれ、茶菓や酒肴で宴会をした。このような年中行事は、武家も町人も区別なく行われていた。年中行事には商家や職人の家で特有の年中行事というものはほとんどなく、年中行事の多くは江戸なら江戸に住む人々には共通の行事なのである。明治六年(一八七三)一月、五節句は廃止されたが、民間行事として続けられ、現在では、五月五日が、こどもの日として祝日となっている。
端午の節句は、もともとは女の祭であったが、中国伝来の端午の節句と結びついて、いつしか男の行事として定着して今日に至っている。もともとは、菖蒲冑(兜)は飾るものではなくて子どもが被るものだったが、時代の変化とともに冑人形となり室内に飾るものとなった。大坂で武者人形を飾ることはかなり遅い時代になってからのことだ。
幕府の年中行事
幕府の年中行事は、年始から始まる。元旦には御三家、御三脚、加質藩主、譜代大名、二日には外様大名、御三家や御三脚の嫡子(跡継ぎ)、和衣役(旗本の中で、紋のない礼装である布衣の着用を許された者)の旗本、三日は無官の大名や御用達商人などが年始に登城した。三日には能を見る御謡始(おうたいはじめ)がある。これに並ぶ祝日は五節句で、諸大名が登城し、祝儀を言上する。ほかにも、六月一六日の厄除けのための嘉祥(かじょう)では将軍から菓子が下され、八日一日の八朔では諸大名から太刀馬代献上があり、一〇月の最初の亥の日に当てられた収穫祝いの玄猪では将軍から餅が下される、などの祝日があった。砧に八朔は、徳川家の江戸打ち入りの日として重視された。
諸大名の登城は、この日から原則として毎月一日、一五日、二八日の月次御礼かある。ただし、登城が頻繁になるのを避けるため、一・二・三・八月の一日、六・七月の一五日、三・五・六・八・九・一〇・一一月の二八日は、月次御礼がなかった。
元服
主に男子の成人式をいう。「元」は首のこと、「服」は冠のことで、成人に達した男子が、髪形や服装を変え、社会に加わる儀式である。元服のときに烏帽子をかぶせる加冠役を烏帽子親といい、生涯保護者としてふるまった。江戸時代の武家では、前髪を落として月代(額から頭頂部にかけて剃りあげた部分を剃り、幼名から大人の名前に変わる。農村でも元服があり、若者組に入り、村の祭りや会同に参加できる資格をもった。江戸の大店でも元服すると丁稚となり、給金を与えられ、商いを任せられるようになる。
農村や商家では、実際に働きを要求されるので、元服は一七歳前後だが、武家では一五歳前後が一般的であり、跡取りの資格を確立させるため、それよりも早めに元服させることも多かった。女子の場合は、初潮の開始をもって成人とされることが多く、平安時代(七九四~12世紀末)の公家では初めて裳を着けるため、着裳(ちゃくも)といわれ、着裳後は眉を剃り、お歯黒を付けた。
隠居
家督を譲って世代交代を行うことをいう。たとえば、徳川家康は隠居したのち、大御所として若い将軍の政治を後見した。隠居することが政治からの引退ではなかったのである。一方、仙台藩主・伊達綱宗のように、行状に問題があったため、重臣たちから強制的に隠居させられることもあった。一般の武士の場合、主君に対する奉公義務があったため自由に隠居はできず、主君に認めてもらう必要があった。その多くは老衰や病気による隠居である。これが許されると、同時に家督相続も認められた。
幕府では、法に定められた年齢というものはないが、病気隠居は四〇歳以上、老衰隠居は七〇歳以上とする慣行があった。御三家であると尾張藩は六〇歳、紀伊藩は五〇歳というふうに、一種の「定年」の基準があったが、例外が数多く認められた。これは願い出で認められるものであるから、幕府には七〇歳以上でなお勤務を続ける旗本も少なくなかった。
隠居すると、別に隠別科という手当てが与えられることもある。また、高齢の親が勤務を続けていると、子は家督相続できず、勤務に出る年齢が遅れるが、親が顕職(地位の高い役職)にある場合は、子が役職に登用されることも珍しくはなかった。庶民では、地域によって隠居の憤行は異なる。東北・北陸地方では、人規摸な農業経営が多いことから、いつまでも隠居はせず、農業経営に携わった。畿内では、長男に家督を譲り、次男などを連れて分家隠居する慣行があった。町人では、若いうちに財産を作り、早めに隠居して自由な生活を送ることが理想とされた。