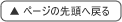江戸の花街と遊女
吉原

元和三年(一六一七)にできた幕府公認の遊郭。日本橋茸屋町の一部に、駿河の宿駅・吉原の旅籠屋・庄司甚右衛門が家康の許可を得て開設したとされる。明麿三年(一六五七)正月一八日の明暦の大火(振袖火事。一月一八日=太陽暦三月二日)により全焼し、同年八月に浅草寺裏に移転した。移転後は、夜間の営業も行われるようになり、元禄(一六八八~一七〇四)のころに最盛期を迎えた。
吉原で働く遊女には太夫、格子、局女郎、散茶など、ランクがあった。そのトップである太夫と枕を交わすには、客が三回以上遊郭に登楼しなければならず、気に入らなければ太夫の方から客を振るなど、非常に格式が高かった。太夫が客に会うため、若い衆の先導で、新造(一六~一七歳以上の女郎)や禿(高いランクの遊女の候補生である少女)をともなって、揚屋(客が太夫や格子と遊ぶための宿)に出かける様子を「花魁道中」という。太人は、初期のころは没落した武家の娘が多かったといわれ、幅広い教養をもち、庶民のあこがれの的としてファッションリーダーでもあった。下層の遊女たちは、北陸の貧農など下層階級出身の者で、過酷な労働のため病気にかかることも多く、二〇代で死ぬものも珍しくなかった。
江戸時代、吉原は様々な作品に措かれているが、その客は金を持っている武士か町人だった。同じく金を持っていた歌舞伎役者がまったく措かれていないのは、歌舞伎役者が吉原へ揚がるのを法令で禁止していたからである。役者が行けたのは寺社詣でか物見遊山くらいである。もっとも、吉原が女性ばかりの悪所なら、歌舞伎役者のいる芝居小屋は、男の娼婦とでもいう男娼ばかりの悪所であったという。
花魁・太夫
「太夫」は、金春太夫や観世太夫でわかるように、能役者の第一人者を呼ぶものだったが、遊廓の最高級遊女の名称としても使われるようになった。吉原の高尾太夫、上方(京都~大坂地方)の吉野太夫などが有名で、代々襲名した。吉原の初代高尾太夫は、仙台藩主・伊達綱宗の相手である。太夫の相手は大名クラスの武士や大町人で、なじみになるためには初会、再会、三会目と最低三回は通わなければならず、一度の登楼に一〇〇両以上の金がかかった。
妓楼(遊女屋)の方でも、太夫養成のために大金をかけた。容姿がよく利発な禿(かむら)をその妓楼の太夫に付けて所作を学ばせ、毎日、身体を磨かせ、その合間に茶や花や香や書画、音曲などの稽古をさせ、一流の女性として育てあげてたのである。「花魁」というのは太夫の別名で、秀が「おいらんとこの姉さん」というのが縮まって「おいらん」となったということである。武士が窮乏して町人中心の時代になると、太夫の存在価値も薄れ、宝暦(一七五一~六四)の末年には吉原に太夫の称号をもつ遊女はいなくなり、格子がそれに代わった。
遊女と階級
元和三年(一六一七)、庄司甚右衛門という者が吉原の創設を幕府から許されたとき、遊女には太夫、格子、端女郎の三つの位付(階級)があった。太夫は最高級の遊女で、揚屋に行って呼ぶ。格子は、格子の中で着飾っていたことから呼ばれた名称であろう。寛文(一六六一~七三)のころ、江戸市中にいた私娼が摘発され、吉原に送られ、格子の下に散茶という階級ができた。散茶とは粉になった下等のお茶のことで、振らずに出る、すなわち誰でも望む者の相手をしたことからこう呼ばれたという。つまり、太夫や格子は、助女か客を気に入らなければ拒否することもできたのである。
その後、遊女の階級は増え、享保(一七一六~三六)のころには、太夫・格子・散茶のうめ茶、五寸局、三寸局、なみ局、次の階級が置かれ、八階級となった。ただ、これは階級というより、揚代の値段の差で細かく分けられただけであろう。ちなみに、最下級の遊女を二朱女郎ともいったが、これは揚代が二朱だったことによる。
遊女の数は江戸中期で二七〇〇~二八〇〇名であったとされる(元禄2年〔一六八九〕、『吉原大画図』)。初期の太夫の揚代は昼夜通しで七〇匁、格子で同五〇匁であった。
吉原細見

吉原で遊ぶ客のために作られた案内書が『吉原細見』である。書名は『吉原袖鑑』『吉原雀』『吉原買物調』などさまざまだが、次第に『吉原細見』の名が定着した。これには、吉原の地図、茶屋のリスト、遊女の名前や位付、揚代などが明記されている。享保二〇年(一七三五)の『吉原細見』では、太夫八二匁、かうし(格子)六〇匁、さんちゃ(散茶)三〇匁とされている。また、人数は、享保から天明までは約二五〇〇人、寛政三年(一七九一)以降は急に増えて四〇〇〇~七〇〇〇人ほどもいたことがわかる。
一八世紀以降、『吉原細見』は、浮世絵版画などを盛んに出版した江戸の地本問屋・蔦屋が版元となり、有名な文化人に序文を吉書かせて刊行し、江戸市内に売り歩かせた。
間夫狂い
多くの男性に身を任せる遊女に、真実というものはなかったが、しかし相手とする男性すべてに不真実だったかといえば、そうでもない。つらい勤めであったがため、誰か一人の男性には真実で尽くそうとすることもあった。そういう相手を間夫(まぶ)といい、すべてを捧げてその男に尽くすことを間夫狂いといった。
歌舞伎『助六』では、遊女・揚巻に、金持ちの遊客から間夫の助六が罵倒されたとき、「間夫がなければ女郎は闇」と言わせている。ただし、遊客に向かってこのように言えば、もはや吉原で生きていくことは難しい。そのため、そうした心を隠して勤めるのが、一般的だったのだろう。