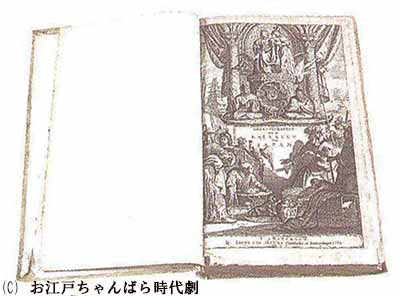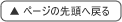世界から注目された黄金の国ジパング
江戸時代には、北海道を除く日本各地で鉱山が開発された。鉱山は、日本の一大主要産業であり、鎖国政策時代にあっても、世界中から注目されていた。図には、「IVAMI(石見)Munes d'Argent(銀鉱山)」とあり、日本各地の鉱山が世界地図で把握されていたことがわかる。
モンタヌスの『日本誌』
日本人は、外国人にどのように見られたか。江戸時代初期、オランダ商館員として日本に来て、商館長にまで昇進した日本通のフランソア・カロンの『日本大王国志』(幸田成友訳)が、ヨーロッパにおける日本認識の基礎となった。本書は、1636年、オランダ東インド会社総督の質問に対するカロンの回答を刊行したものである。
まず統治形態だが、日本では、「皇帝(将軍のこと)」が最上の支配者で、多くの「国王(大名)」「領主(武士)」がそれに服従した、という。現在からみると、将軍の上に名目的な君主として天皇がいたことが無視されているが、当時の天皇には実質的な権限がほとんどなかったので、むしろ正しい認識ともいえる。また、皇帝は、時々、小失策をした国王および領主を領地から放逐し、流罪または死罪に処し、彼らの領地・財宝・富および収入をいっそう従順な他の者に与える権力をもっている、という。将軍が諸大名を改易・転封する権力をもったことは、ヨーロッパの国王と貴族の関係を考えれば、驚くべき強大な権力だと認識されたのである。意外なことは、上は皇帝から下は小さな市民(町人)に至るまで、およそ主人たる者は、臣下従僕(しんかじゅうぽく)に対し裁判の権を有していた、と書いていることである。町人は使用人に対する裁判権をもっていなかったが、実際にはそういうこともあったのかもしれない。
刑罰については、「貴族・兵士(ともに武士のこと)にして罪が死にあたる者には切腹を許して自らの生命を絶たしめるが、商人市民その他身分の低い者は裁判によって死刑に処す」と、刑罰としての切腹を正確に認識している。カロンが「商人は少しも重視されることはなく、かえって軽視されている」と書くのは、ヨーロッパで商人が重視されるのに対し、日本ではそうでないのが驚きだったからだろう。 子どもについては、7歳から12歳ぐらいでもひじょうに賢く温和で、7歳以下の子どもは学校に行かないが、遊戯や友達の集会が教育にかわっている、7歳から9歳ぐらいになると徐々に読書や習字を始める、と書いている。イエズス会士同様、子どもに対する評価は高い。とくに注目すべきは、次の一節である。「日本人は強情な国民で、鞭撻(べんたつ)を以て迫るべきものではない」
ヨーロッパ人は、アジアの多くの国で、軍事力をもってその国の人々を従わせてきた。しかしその方法は、日本では決して成功しないであろうことを強調しているのである。 日本人は、名誉をひじょうに重んじ、恥を知り、名誉を守るためには喜んで命を捨てる。こうした特質から、「この国民は信用すべしと認められる」と断言している。さすがに日本通とされるカロンだけあって、よく日本人の特質を見ているようだ。ただし、この時代にヨーロッパに紹介された日本の視覚的なイメージは、モンタヌスの『日本誌』で形成された。将軍の裁判・切腹・大仏など、あきれるほど奇妙なものである。ヨーロッパ人にとって日本は、中国やインド、イスラム諸国などのイメージと末分離なものだったのである。
申維翰(シンユハン)の『日本閲見雑録』に見える日本の風習
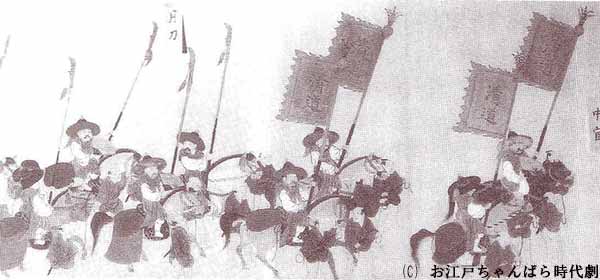
享保4年(1719)、8代将軍吉宗の就任を賀して来日した朝鮮通信使に製述官(せいじゅつかん)として随行した申維翰は、有名な『海遊録』(かいゆうろく)という紀行文のほか、『日本見分雑録』という日本と朝鮮を比較した文章を残している。隣国である朝鮮の使節は、日本をどのように見たのだろうか。申は、日本の宮殿の造作が白木中心になされていることを「精潔を極め」と褒め、また器物や船の造作に使われている黒漆が鏡のように光沢があることに驚いている。また、夏の暑い盛りでも蝿が少ないことに感心している。申も、ヨーロッパ人と同じく、日本の清潔さに注目しているのである。こうした工芸には感心しながら、「礼法はまったく明らかでない」と批判する。なぜなら、日本では平民の富豪が王侯とおごりを競っているからだという。朝鮮では身分によって家屋の規模が遣うが、日本でよそのような規制がないように見えたのであろう。
しかし、日本でも豪商の家は立派だったかもしれないが、大名の藩邸のような規模のものはとうてい建てられないし、門もなかったはずである。何を誤解したのかよくわからない。ただし、申が見た豪商の家が立派だったことは推測できる。多くの豪商が生まれた元禄期の様相を、よく物語っているといえよう。
日本の兵制に関しては「もっとも精強』とし、民はひとたび兵となればその生死はすべて将官の手にゆだねられる、としている。武士が主君のために命を捧げることを正確に認識しているのである。申の「(武士は)いたる処で他人に劣るような佩剣(はいけん)を見せてはならず、それが劣れば人間仲間に列することができない」という言葉は、日本の武士の姿を正確に言い当てている。武士は臆病と見なされただけで身の破滅だった。おもしろいのは、刀槍の傷が顔にあれば勇者とされる、と書いていることである。江戸時代には顔に傷をもつ者が多く、しかもそれを誇っていたことが証言されている。兵では、甲斐の騎兵と薩摩の剣士が「もっとも驍勇(ぎょうゆう)にして敵しがたい」とし、兵器としては剣と銃が精巧で、長短の刀を持つ者は、長いものは「撃刺」に使い、短いものは相手めがけて投げる、としている。その動作は俊敏で、相手は刀を受け、立ったまま死ぬという。小刀は、平和な時代のなかでも意外に有用な武器として使われていたのかもしれない。
女性の容貌については、「多くの場合、なまめかしくて麗しい」と褒めている。化粧をしなくても肌がきめこまかくて白く、化粧をしている者も肌が柔らかくてつやつやし、自然に見えた。しかし、男女関係については批判的である。日本では家に必ず浴室を設け、男女がともに裸で入浴し、白昼から互いになれあい、夜はまた必ず灯火をつけて淫を行ない、興をかき立てる「具」を備えて、歓情を尽くす、というのである。「具」とは浮世絵の春画や媚薬のことのようで、どうしてこういうことを知ったかはわからないが、貴重な証言となっている。たしかに春画は大量に流通していたし、張形なども使われていた。男女関係以上に申が嫌悪感をもったのほ、男色の風習だった。日本の大きな町には必ず娼家があって繁盛しているが、娼婦以上に男を惑わすのは男娼だった。申は、応接役の対馬藩儒学者雨森芳洲に、「貴国の俗は奇怪きわまる」と批判した。すると雨森は、笑って、「学士はまだその楽しみを知らざるのみ」と答えたという。日本の武士たちの風習をよく物語るエピソードである。
ペリー提督日本遠征記

嘉永6年6月3日(西暦1853年7月8日)、浦賀に来航したペリーは、奉行を僭称(せんしょう)した浦賀奉行所与力香山栄左衛門らを旗艦サスケハナ号に乗せ、アメリカ大統領の国書を渡すことについて協議した。そのとき、日本人の奉行たちについて、次のように述べている(三方洋子訳『ペリー提督日本遠征記』)。「日本の役人たちは、育ちのよさを示すかのように、紳士的冷静さと節度あるマナーを終始崩すことはなかったが、とても社交的で、自由に陽気に会話を楽しんだ。彼らのもつ知識や情報も、洗顔されたマナーや人なつこい気質に劣らなかった。育ちがいいばかりではなく、教養程度も高かった」香山らは、地球儀を見せられると、ワシントンとニューヨークを即座に指さし、またヨーロッパの国々についても正確に示した。パナマ運河が完成したかどうかまで尋ねて、ペリーを驚かせた。また、蒸気船の艦内を見学したときも冷静で、最新式の大砲の名も正確に言った。対外的な危機意識が強かっただけに、武士たちはかなり勉強していたのである。ただし、幕府の役人には決定権がなかったので、ペリーの要求はなかなか聞き入れられなかった。ペリーはこれを不誠実な対応と考え、日本人はずるい性質をもっていると断じている。
翌安政元年三月、日米和親条約を結んだペリーは、領事館が置かれる予定の伊豆の下田に赴いた。彼は、日本の家屋や女たちについて次のように書いている。町の清潔と衛生については、「われわれが誇る文明国よりもずっと先を行っている」と高く評価するが、下田の名主の家は、「家の中は一間きりの非常に質素なものだった。床には柔らかなマット(畳)が敷かれ、油紙を張った窓から採光していた。へたな絵が掛けてあり、どこにでも見られる赤いベンチが置いてあった」と散々である。
日本人女性については、既婚者の風習であるお歯黒に閉口し、「この習慣が夫婦の幸せに貢献することはないように我々には思える。接吻は求婚時代で終わってしまうのだろう」と述べている。たしかに、われわれが見てもお歯黒は異様であり、ペリーの印象も納得できる。
未婚女性については、ひじょうに好意的な評価である。「日本の女性の見た目は悪くない。若い娘はスタイルも悪くないし、おおむね可愛い。何よりいきいきとしていて、しつけがよい。それは自分たちが正当に扱われているという誇りからきているもののようだ。友達や家族との日常では女性もそれぞれ役割があり、訪問しあったり、お茶の会をもったりしているのは、アメリカと同様である」日本女性は、女性の権利の強いアメリカなみにその地位を認められ、自由に暮らしていたのであった。当時のアジアにおける女性の地位を考えるとき、公平な見方だと考えていいのではないだろうか。ただし、公衆浴場での混浴の風習には、「みだらである」と眉をひそめている。翌年、条約批准を伝えるために日本に戻ってきたアダムズ中佐は、地震で大きな被害を受けた日本人が、座って不運を喋くのではなく、気を取り直して復興の努力をしていることに感動している。日本人のエネルギーと回復力は、幕末に日本に来たアメリカ人も十分に認識していたのである。