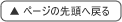鎖国と貿易
幕府は、新たな鎖国令を発し、ポルトガル船の来航禁止、沿岸警備の徹底を命じた。これにより、九六年続いたポルトガルとの貿易に終止符が打たれることとなった。しかし、これを実施するには、ポルトガルが運んでいた輸入品をいかに確保するかが問題となった。幕府は決定に先立ち、オランダに対しポルトガルに代わり生糸や絹織物などの供給が可能か打診し、十分に可能であるとの返答を受け、ポルトガル船来航禁止に踏み切ったのである。
また、幕府はキリシタンの脅威を再認識させられた島原・天草一揆を意識し、唐船・オランダ船に対してもキリシタンの乗船を禁止。九州諸大名に対し、沿岸監視と異国船の長崎回航を命じた。寛永12年の鎖国令で、日本船の海外渡航と海外在住日本人の帰国が全面的に禁止され、日本人の海外往来禁止が確定している。今回のポルトガル船来航禁止を内容とする鎖国令は、幕府による鎖国の総仕上げであり、これにより鎖国が完成したことになる。
一七世紀の東アジア情勢
寛永二一年、三世紀近く中国を支配してきた明朝が倒れ、満州族の清朝が成立した。明末に東アジア海域の貿易活動で勢力をのばした鄭氏(ていし)一族は、清朝の支配に抵抗して、南中国沿海部、のちに台湾に拠点を置き、国家といえるほどの勢力を保っていた。清は、当初鄭氏の勢力を抑えるため、強力な海禁政策(中国人の海外渡航の禁止)をとった。
清が鄭氏を滅ぼして、沿海の貿易を手中に収めるのは、家綱から綱吉の治世(一六八〇年代)のことである。一方、一六世紀以来東アジアの市場に参入していたスペイン、ポルトガルは徐々に勢力を失い、一六四〇年頃を境に、オランダ東インド会社が取って代わった。オランダは、両国が日本通航を禁止されたため、彼らにかわって日本貿易を行なうようになり、日本人の海外渡航禁止で途絶した朱印船貿易の交易路と市場をも手に入れて、莫大な利益を上げた。
中国生糸(白糸)と日本銀の交換は、一七世紀に、世界でもっとも儲かる貿易といわれた。中国の海禁政策と日本の鎖国政策により、その担い手はポルトガル人・日本人からオランダ人・中国人へと移った。一八世紀には、日本銀の枯渇により、この貿易も衰える。
貿易拠点としての長崎
幕府は、貿易再開交渉のため長崎に来航したポルトガル船を焼き、パチェンコら乗務員61名を斬首に処した。鎖国後、初めてとなるポルトガル船が長崎に来航したのは、この五月一七日。これに対し幕府は、この日、前年出された渡航禁止令を犯したことを理由に、乗組員らを処刑したのである。また、ポルトガルに対し鎖国令実施の意思をアピールするため、死罪を免れた水夫ら13人を唐船でマカオに送り返すとしている。
日本人が海外渡航を禁止されても、中国産の生糸や絹織物・蘇木(染料)・鮫皮・鹿皮(武具などの材料)・薬種(香料)・更紗などのアジア産品、はては羅紗などヨーロッパ産品の、日本での需要は衰えることがなかった。日本の対外交易ルートは、朝鮮経由、琉球経由でも確保されていた。しかし、一七世紀なかばの海禁政策の合間を縫って東南アジアに進出していた中国のジャンク船と、彼らから生糸を仕入れたオランダ東インド会社船が、渡航を許されていた貿易港長崎は、きわめて重要な役割を担っていた。キリシタン禁制、寛永期のいわゆる鎖国政策によって、変容を余儀なくされた長崎だったが、『寛文長崎屏風」の描く寛文一三年(一六七三)には、見事に近世都市として再生し繁栄していた。しかし、一六八〇年代には鄭氏の滅亡により清が海禁政策を弱めたため、長崎に来航するジャンク船が急増して、幕府は銀の流出を抑えるようになった。また、中国商人の密貿易も増え、元禄年間(一六八八~一七〇四)には唐人屋敷がつくられ、中国人の長崎市中居住は禁止されるようになった。唐人屋敷に付随して、新地と呼ばれる中国貿易用の倉庫が並ぶ埋立地が作られた。一八世紀に入り、日本の金銀山が枯渇しはじめると、徳川家宣・家綱に仕えた儒者新井白石は、金銀の国外流出を制限しようとし、その結果、正徳五年(一七一五)「正徳新例」(しょうとくしんれい)が出された。
鎖国の定着と文化受容
『寛文長崎図屏風』の描く寛文一三年には、イギリス船リターン号が長崎に来航して貿易許可を求めたが、幕府は拒否した。イギリス王室とポルトガル王室が姻戚関係にあることが、そのおもな理由であった。デンマークの東インド会社も日本貿易を企図していたが、実現はしなかった。一六八〇年代には、カンボジア国王船が貿易を求めて長崎に来航したが、それも幕府は認めなかった。こうして、幕府の対外政策は、日本人の海外渡航を厳しく禁止するだけでなく、実際上、貿易の相手国を限定していった。その結果、のちに鎖国と呼ばれる体制が、徐々に定着した。
「鎖国(国を鎖す)」という言葉は、長崎のオランダ通詞だった志筑忠雄が、一七世紀に出島商館に医師として在勤したことのあるドイツ人ケンペルの『日本誌』の蘭訳本付録の一章を、享和元年(一八〇一)に翻訳し、『鎖国論』と題したときに生まれた。貿易の相手国が限定され、貿易量も制限されると、貿易の質もだんだん変化していった。中国商人もオランダ東インド会社も、日本に持ち込む商品を、利益率の高い品物に絞るようになった。また、漢籍や蘭書の輸入は、文化的な重要性をもつようになった。織物などの商品も、とくにヨーロッパ製のものは「阿蘭陀渡り」として、ある種のブランド価値をもつようになり、文化輸入の側面をもった。しかし実際には、イギリス産品が広州経由のジャンク船によって輸入されることもあった。また、船体の安定を保つために底荷(バラスト)として砂糖が輸入された。一方、輸出品は銅と俵物(おもに蝦夷地産の海産物)が主流となり、ほかに漆器や磁器などの工芸品も輸出された。
海外情報誌の「風説書」
幕府は、貿易港を長崎に絞ると同時に、来航する中国人とオランダ人に、ポルトガル人などの陰謀に関する情報があれば提供するように義務づけた。唐通事(中国語の通訳で中国人の世話係・監視役でもある)やオランダ通詞は、この法令を受けて、船が到着すると、ほぼ毎回、海外情報を聞き出すようになった。中国人からの情報は、口頭だけでなく、漢文の文書で提出されることもあった。一方、オランダ人からの情報は、通詞が聞き出し、和文の文書に仕立て、長崎奉行が幕府に提出した。これらの海外情報を記した文書を一唐(船)風説書」「オランダ風説書」と呼ぶ。
「唐(船)風説書」は、一八世紀なかばまでは中国・東南アジアの情報を提供したが、それ以降は、一九世紀なかばまで、あまり重要性をもたなかった。「オランダ風説書」は、幕末までほぼ毎年、アジア、ヨーロッパのみならず、アフリカ、アメリカ大陸に及ぶ情報を提供しつづけた。またオランダ商館長は、当初毎年、のち四年に一回の江戸参府を行なった。その際の江戸での定宿長崎屋には蘭学者が集まり、ひとつの文化発信地となっていた。